学習机をいつ買うべきか、迷っていませんか?
入学のタイミングで用意した方がいいのか、子どもが必要になるタイミングを待ったほうがいいのか……。買っても使ってくれなかったらどうしよう、と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実際にわたしも、我が子の学習机を買うタイミングには本当に悩みました。上の子と下の子、それぞれのタイミングで購入してみて、使い方や子どもの気持ちに大きな違いがあることに気づきました。この記事では、そんなわが家での体験をもとに、学習机を買うベストなタイミングについて、わかりやすくお伝えしていきます。
同じように迷っている方の参考になれば嬉しいです。ぜひ最後までお読みください。
学習机はいつ買う?我が家の経験から見えたベストなタイミング
上の子は小学校入学時に購入。親の想いと現実のギャップ
我が家では、長女が小学校に入学するタイミングで、はじめて学習机を購入しました。
この時期に学習机を選ぶときは、親の思いと子どもの気持ちをうまくすり合わせることが大切です。
親としては、「長く使えること」や「どんな部屋にもなじむこと」といった実用性を重視し、白くてシンプルなデザインの机を検討していました。しかし、当時の娘はちょうどパステルカラーに夢中になっていた時期で、キラキラした可愛いものが大好き。白と薄むらさきの可愛らしい学習机を欲しがっていたのです。
中学生になっても使ってほしいと思っていたため、親子で何度も話し合い、最終的に白を基調としたシンプルな机に決めました。その過程では、親の考えと子どもの気持ちをすり合わせるのに苦労したのも事実です。
娘が少しでも気に入ってくれるように、ワゴンの取っ手は本人の希望でキラキラのパーツに付け替え、“ときめき”の要素をプラスしました。幼い子どもは、そのときの好みに素直に惹かれるのが自然で、将来まで使えるかどうかは、なかなか想像できないものですよね。
今では中学生になり、「白のシンプルな机を選んでよかった!」と言ってくれるようになりました。親の思いと、子どもの好みをぴったり一致させるのは簡単ではありません。少しずつ歩み寄ると、親子ともに納得できる選択ができるでしょう。
実際に机を使いはじめたのは高学年になってから
自分の机ができた!と喜んでいた娘でしたが、低学年の間は勉強のほとんどがリビング中心。学習机は、お絵描きをしたり、ビーズで遊んだりと、趣味のスペースとして使っていました。
本格的に学習机を使いはじめたのは、宿題が増える高学年になってから。中学生になった今では、日々の勉強に欠かせない場所になっています。
結果的に活用できたものの、本人の好みの変化を見ると、もっと必要性を感じたタイミングで買ってもよかったのかも?と思うようになりました。親が準備してあげたい気持ちと、子どもが実際に必要と感じるタイミングには、少しギャップがあるのかもしれませんね。
下の子は5年生で購入。結果的に正解だった
長女の経験をふまえて、下の男の子は5年生になってから学習机を購入しました。
本人の気持ちがしっかり固まったうえでの購入だからこそ、無理なく机に向かう習慣ができていると感じています。
きっかけは、勉強系の習い事を始めたこと。宿題の量が増え、自分のペースで集中できる環境が必要だと感じ、「そろそろ机を用意してみようか?」と声をかけました。本人もリビングでは集中しづらいと感じていたようで、「ほしい!」と前向きな反応があり、すぐに近くのインテリアショップへ見に行くことになりました。
本人が選んだのは、木目と黒を基調にしたシンプルでかっこいいデザインのデスク。好みがはっきりしてくる年齢なので、自分で選んだ机には自然と愛着も湧くようです。子どもっぽいデザインではないため、大きくなったら恥ずかしくて使えなくなる心配もありません。
学習机としての役目を終えたあとも、趣味や作業用の机として活用できるデザインなので、長く使えて無駄がないのも嬉しいポイントです。
早めに準備してあげたいという親心は、きっとどのご家庭にもあると思います。しかし、子ども自身が「ほしい」「使いたい」と感じたタイミングこそが、その子にとっていちばん自然で、無理なく学習机を活用できる時期なのかもしれません。
学習机の購入タイミング別メリット・デメリット
小学校入学時に買うメリット・デメリット
小学校入学のタイミングで購入すると、新しい生活のスタートとして気持ちの切り替えにもなり、祖父母からの入学祝いとしても選びやすい点がメリットです。ただし、低学年のうちはリビング学習が中心になりやすく、使われないままになってしまう可能性もあるため、子どもの性格や環境に合わせて慎重に考えることが大切です。
低学年のうちから学習机を使う子は、自分だけの落ち着ける空間を持ちたいタイプの子が多いようです。図工や工作が好きで、じっくり取り組むのが得意だったり、リビングがにぎやかすぎて集中できないと感じたりする子は、自然と机に向かう場面が多いでしょう。
高学年以降に買うメリット・デメリット
高学年になり、本人の意思で机を選ぶと、納得して使ってくれる可能性が高まります。自分の学習スタイルが少しずつ確立し、集中できる環境を求めるようになるからです。
この時期は宿題も増えるため、自分の机で勉強する気持ちが自然に芽生え、机への愛着も生まれやすくなります。ただし、購入のタイミングを見失いやすいため、子どもの様子を見ながら家庭内で話し合うことが大切です。
中学進学時に買う家庭の考え方
中学進学時は学習内容が大きく変わり、机での勉強が本格的になるときです。この時期は必要性を実感しやすく、購入しても無駄になりにくいのが魅力です。
高校生・大学生になっても使えるデザインを選べば、長く活用できるのもポイント。ただし、成長期は何かと出費が重なる時期でもあるため、予算計画は慎重に立てておくことが大切です。
後悔しない学習机の選び方
シンプルで飽きのこないデザインがおすすめ
最初から完璧なセットをそろえるよりも、シンプルな机をベースに、ワゴンやラックなど必要に応じて後から足せるスタイルがおすすめです。
収納を増やしたり、不要になったら減らしたりと、成長や生活の変化に合わせて柔軟に対応できます。買い替えの必要がないので、無駄もなく安心です。
子どもの好みは成長とともに変わるので、カラフルなデザインよりも、白・ナチュラル・木目などのベーシックな色味を選んでおくと、飽きずに長く使えます。
将来まで見据えた柔軟な目線で子どもと一緒に選ぶと、後悔しない机を選べるでしょう。
取っ手やワゴンなど、カスタマイズで子どもの好みに寄せる
子どもが机を気に入って大切に使うには、少しでも自分らしさを取り入れる工夫がポイントです。
取っ手を好きな色や形に変えたり、デスクマットやカバーを本人に選ばせることで、子ども自身の好みを反映させた空間がつくれます。椅子にふわふわのクッションを置いたり、棚にお気に入りの小物を飾ったりするのも効果的です。
こうしたちょっとした工夫が、愛着を持って使いたくなる特別な机につながります。選ぶプロセスに子どもを参加させることで、自立心や責任感も育まれますよ。
将来的に使い道がある机を選ぶと安心
学習机としての役割が終わっても、パソコンデスクや作業机として使えるものなら、無駄にならず長く活用できます。
我が家も下の子の机は、趣味や作業用として使えるようシンプルなタイプを選びました。飽きのこないベーシックなデザインを選んだことで、年齢やライフスタイルが変わっても違和感なく使い続けられます。
将来的に処分せずに活用できる家具として考えると、デザインの選び方も大切な視点になりますね。
【まとめ】学習机はその子のタイミングを見きわめて
学習机は、早く買えばいいものではないと思っています。
入学のタイミングでそろえたくなる気持ちもありますが、実際に使いはじめる時期は子どもによってさまざまです。大切なのは、子ども自身が「使いたい」と思ったときに用意してあげること。そのほうが自然と机に向かう習慣が身につき、長く大切に使ってくれるようになります。
親の思いと子どもの気持ちをうまくすり合わせながら、その子にとってちょうどいいタイミングを見つけていけたら安心ですね。まずは、日々の様子を少しだけ観察してみることからはじめてみませんか。きっと、その子に合った「学習机が必要なタイミング」が見えてくるはずです。
その子にちょうどいい学習机が揃ったなら、その子の能力を伸ばす時期かもしれません。いろいろな経験を積ませてあげてください👇![]()
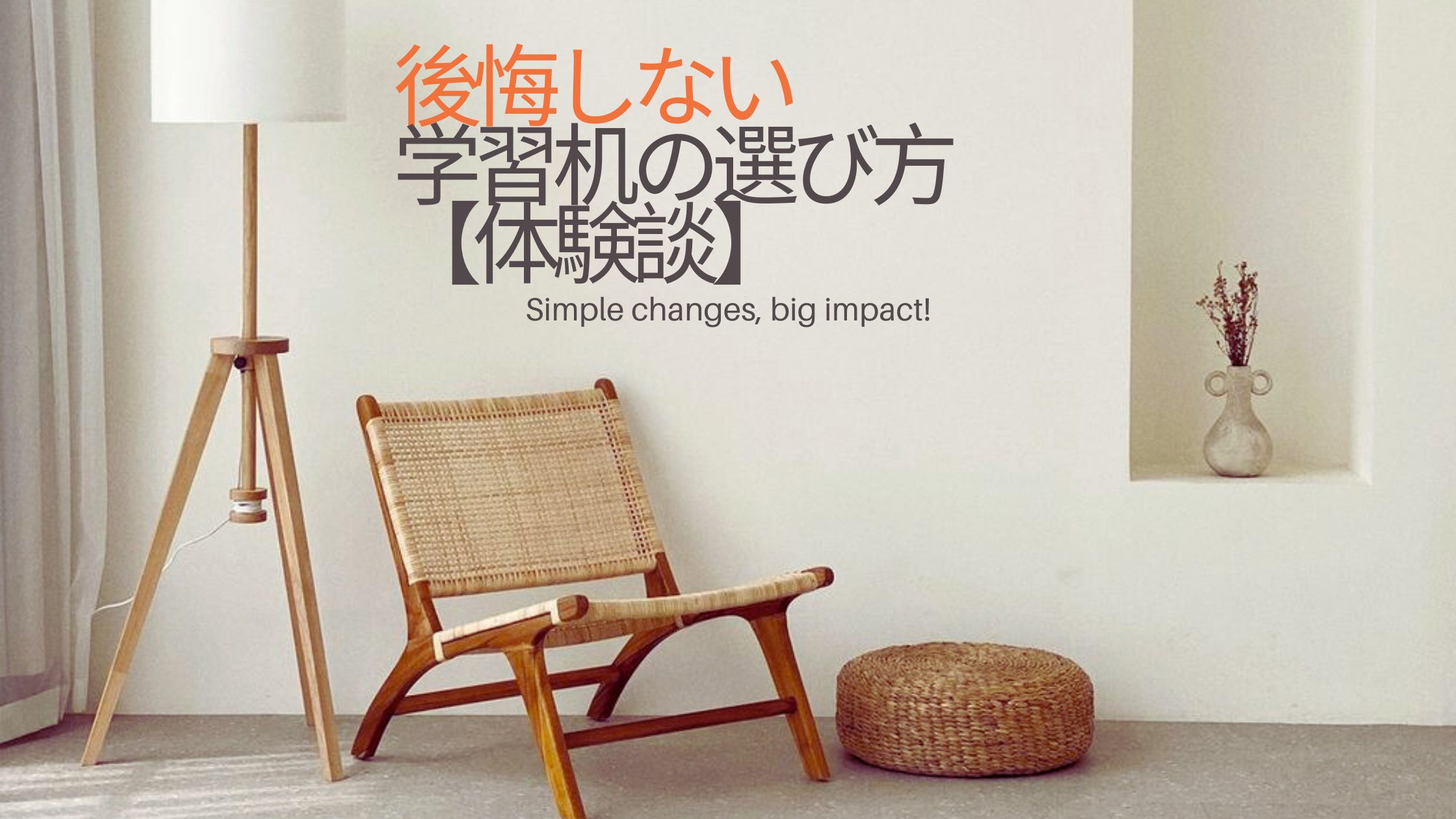

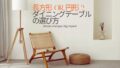
コメント